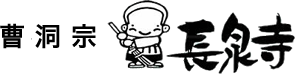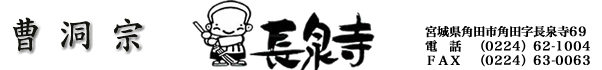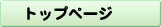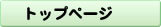とはいえ、最近とくに感じるのは、時間の流れの速さです。実はこの二か月ほど長泉寺を留守にしておりまして、そのせいか余計に月日の早さを思わされます。年を重ねるにつれて、時はますます速く過ぎていくようで、「これは一体どういうことなのだろう」と考えることがあります。皆さんも、「若いころは一年がとても長く感じられたのに、今ではあっという間に過ぎてしまう」と思われたことはありませんか。
仏教では、この現象を「諸行無常」として説きます。すべては変わり続け、同じ時は二度と訪れません。それにもかかわらず、私たちはその変化を見慣れ、つい「同じ日常」と思い込んでしまう──その思い込みこそが、時をさらに早く感じさせるのかもしれません。
そこで、AI(ChatGPT)にその理由について聞いてみました。
年を重ねるほど時の流れが速く感じられる理由については、心理学や神経科学でもいくつかの仮説が提唱されています。
第一に、「人生の割合」説です。
10歳の子どもにとっての1年は人生の10分の1ですが、50歳の大人にとっては50分の1に過ぎません。年齢を重ねるほど、1年が人生全体に占める割合は小さくなり、相対的に短く感じられるのです。
第二に、新鮮さの減少です。
子どもの頃は初めての経験が多く、脳は大量の情報を処理して記憶に残します。しかし大人になると日常がパターン化され、新しい出来事が減るため、記憶の密度が下がり、振り返ったときに「短く」感じられるのです。
第三に、生理的変化です。
加齢とともに脳の情報処理速度や神経伝達の働きが変化し、時間感覚そのものが微妙に変わる可能性があります。
これらの仮説はいずれも、「今という瞬間をどう感じ、どう記憶に残すか」が時間の感じ方を左右していることを示しています。つまり、年齢だけが原因ではなく、心の持ち方や日々の過ごし方によっても、時の流れの速さは変わるのです。
では、年齢を重ねても時間をゆっくりと感じるには、どうすればよいのでしょうか。それについても聞いてみました。
心理学や脳科学、そして仏教の教えは、共通して次のような答えを示しています。
第一に、新しい経験を積極的に取り入れること。
旅行や新しい趣味といった大きな挑戦でなくても、通勤路を変える、初めての店に入るなど、日常に小さな「初めて」を加えるだけで、脳は活性化し記憶が濃くなります。
第二に、五感を使って今を味わうこと。
仏教では「念(いまに心をとどめる)」といいます。コーヒーを飲むとき、その香り、温度、舌触りを意識的に感じる。外を歩くとき、風や光の色を観察する。こうした五感の働きが、記憶を鮮やかにします。
第三に、感情を伴う体験を増やすこと。
感動や驚き、笑いといった感情は、ドーパミンの分泌を促し記憶を強化します。仏教の「一期一会」の心で、人や出来事と向き合えば、一瞬の価値が高まります。
第四に、振り返りの時間を持つこと。
一日の終わりに印象的な出来事を三つ思い返す習慣は、脳の記憶定着を助け、時間を「長く」感じさせます。
季節は巡り、時は光陰矢の如く過ぎ去ります。しかし、今を丁寧に味わい、日常に新しさを見いだすことで、私たちはその速さの中にも深い充実を見いだすことができます。
年を重ねることは、時の速さを知ることでもあります。そしてそれは、無常を深く味わう機会でもあるのです。
私は昭和20年当時、16歳の学生で、当時の実情を実感しているのは皆様も同じと思います。今思うと働ける人は少なく、老父母と嫁さんで家族を守り、男まさりの力仕事が必要でした。作物に施す肥料もなく人糞だけ、また、農耕馬として飼っていた馬は戦地に供出され、自力で耕すほかなく、辛抱、辛抱の日々でした。終戦直後は、戦地からの復員や疎開等で各家庭では急に大家族となり、食料不足と混乱が重なりました。昭和21年には米価が220円となり、農地改革法や農地調整法、農業協同組合法が公布され、昭和27年には米価が3,000円となり、当時の水田の価格は1反当たり3,000円で米価と同額となったため、各地で田畑の開墾が盛んになり、活気と自活の暮らしとなってきました。
この頃から、高度な化成肥料と改良稲作と精度の高い農業機械等で収穫が増えて米価は3,900円、家庭電化時代の到来とともに、昭和36年には農業基本法が成立し、米価は5,600円に昭和44年には減反政策が始まり、昭和46年には8,631円と高価格になりましたが、減反政策が実施されてから23年間も継続され、山間地ほど転作できなくて原野が多くなり、残念な思いです。
私が心にしていたことは、湿田地の毛萱のドブ田を改良し、近代農業ができるような圃場になるように友達と話し合いを重ね、地域の方々の理解と協力があり、平成5年に「毛萱地区モデル担い手育成基盤整備事業」が完工し、今では担い手の皆様が大型農業機械で働く姿がたくましく、感動と感謝の心でいっぱいです。
結びに、工事完工の歓びは偶然ではないと思っています。過去の苦難に満ちた水田の小さな種が時間を掛けて発芽し、実を結んだ結果であり、その喜びは、皆様の結束の印だと信じています。この耕地を守ってくださるよう切にお願いいたします。
境内の桜も、いよいよ満開を迎えました。寒さもようやく和らぎ、確実に春の訪れを感じられる今日この頃。心の中にも、ほんの少しですが、ゆとりのようなものが芽生えてくる気がします。
最近、『禅僧は語る』(みちしるべ特別編)という冊子を手に取りました。その中に収められていた、中野東禅先生(京都・曹洞宗 龍宝寺住職)による「日月流るるが如し」という文章が、春の季節にふさわしく、やさしく、深く心に響きました。季節のめぐりと共にある仏教の時間観が語られており、まさに今こそ味わいたい内容です。
一、「青葉城恋唄」の歌詞「ときはめぐり」という表現に対して、「時は過ぎ去るものではないか」という意見があったそうですが、「とき」を「季節」として捉えることで、「巡る」ことが受け入れられたといいます。自然の四季が循環するように、「とき」という言葉にもめぐりの感覚を込められる日本文化の特質が、そこに表れています。
二、美空ひばりの「川の流れのように」や、芭蕉の『奥の細道』の冒頭「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり」に見られるように、時間の流れを直線的に捉える一方で、自然の循環や人生の成熟の過程も含んだ、重層的な時間観が示されています。
三、内村鑑三の「人生の四季」では、春・夏・秋・冬を人生に重ね合わせ、それぞれの時期に特有の喜びや悲しみ、成熟があることが語られています。
人生の春ありたり。勇気勃々、希望満々(中略)春は実に喜ばしき悲しき時期なりき。
人生の夏ありたり。議論誇々、主義堂々(中略)夏は実に喜ばしき悲しき時期なりき。
人生の秋は来にけり。感涙滴々、思惟粛々(中略)寂蓼に感謝伴い、孤独に祝福あふるる。秋は実に静かなる楽しき時期なりけり。
人生の冬は来たるべし。しかれども絶望の時期にあらざるべし。また来ん春を望みつつ、過去の恩恵を感謝しつつ、父の家に還るなるべし。(仏の世界)
とくに「冬」を、希望を抱きながら過去に感謝する時期と捉える視点に、悲観ではなく肯定的なまなざしを感じます。
四、会津八一の「日々新面目あるべし」という言葉にも触れられていました。毎日を新たなものとして味わい、心を澄ませて生きること――これは、仏教でいう「正念」、すなわち「今ここ」に意識を向ける教えとも響き合っています。
五、良寛和尚もまた、老年に至ってなお、日々の中に新しい感動を見出し、子どもたちと無心で遊ぶことで、その境地を生きておられました。無心の中にある自由と仏の智慧。そうした「遊び」の精神もまた、私たちが「今」を生きるための大切な手がかりになるのかもしれません(この点については前回の文章でもご紹介しました)。
桜が咲き、やがて散っていくこの季節。私たちの人生もまた、その自然の営みと重なり合っています。流れていくようで、めぐってもいる「とき」。今この一瞬を丁寧に味わうことこそが、仏教が教える生き方なのだと感じます。
年齢を重ねたからこそ、こうした文章に自然と頷いてしまうのかもしれません。
- 良寛の「遊び」から学ぶ-
まだまだ寒い日が続きますが、日が長くなり、少しずつ春の訪れを感じるようになりました。春とともに、卒業や入学など、新たな門出を迎える季節がやってきます。これは人生の大きな節目であり、新たな出会いや挑戦の機会でもあります。そんな変化の時期に、私はふと、江戸時代の禅僧・良寛の「遊び」の姿を思い出します。
良寛は、生涯を通じて名誉や財産に執着せず、シンプルな生活を送りました。特に晩年、彼が大切にしていたのが「子どもたちと遊ぶこと」でした。まりつきやかくれんぼ、鬼ごっこなど、彼は子どもたちと共に無邪気に遊び続けました。ある日、かくれんぼであまりに真剣に隠れすぎ、子どもたちが帰ってしまった後もじっと隠れ続けていた、という逸話も残っています。
では、なぜ良寛はこれほどまでに「遊び」に没頭したのでしょうか。宗教学者の山折哲雄氏は、この良寛の行動を「無心の境地」の実践であったと解釈しています。子どもたちは、計算や打算なく、その瞬間の遊びに夢中になります。その姿は、禅が理想とする「無心」の境地に通じるものであり、良寛もまた、子どもたちと遊ぶことで、その境地を実践し続けたのではないかと考えられます。
仏教においても、「遊び」は単なる娯楽ではなく、精神的な解放や悟りの一環として捉えられています。仏教の教えは、「今を生きること」の大切さを説きますが、まさに子どもたちの遊びは「今、この瞬間に生きる」ことそのものです。良寛の遊びは、まさに禅の実践であり、悟りへの道だったのかもしれません。
また、「遊び」には、人と人とを結びつける力があります。「遊び心を忘れない」という言葉があります。これは、柔軟な発想や創造性を持ち続けることの大切さを示しています。遊びは、上下関係や年齢の違いを超え、互いに対等な立場で関わることができる場です。良寛は、遊びの中にこそ、自由で平等な世界があることを知っていたのかもしれません。
このような視点から「遊び」を考えてみると、私たちの生活においても、遊び心を持ち続けることがいかに大切かが分かります。仕事や勉強に一生懸命になることも大切ですが、時には良寛のように、無邪気に遊び、無心になる時間を持つことが、心の豊かさにつながるのではないでしょうか。
新たな環境へと踏み出すこの季節、良寛の「遊び」の精神を思い出しながら、心に少し余裕を持ち、遊び心を忘れずに過ごしていただければと思います。新しい出会いが、皆さんにとって素晴らしいものとなりますように。
3月11日は東日本大震災が発生した日です。あれから14年が経ちます。震災によって多くの方々が犠牲となり、今なお行方不明のまま見つかっていない方々がいらっしゃいます(昨年の時点で2520名)。その衝撃は私たちの心に深く刻まれ、悲しみは今も、そしてこれからも消えることはないでしょう。
宮城県ではこの日を「みやぎ鎮魂の日」と定め、各地で哀悼の意を捧げています。当長泉寺でもご供養を行い、多くの犠牲者の方々に改めて慰霊の誠を捧げてまいりました。
さて、これはだいぶ前の事でHPへも掲載した話ですが(震災から4年後平成27年)、長泉寺の檀家の方で震災の犠牲となられた方のご遺体が、発生から3年10ヶ月を経て発見され、ご葬儀をお勤めさせていただいたことがございました。ご家族の皆様は、「震災で娘はもう生きていないのではないか」と諦めの気持ちを抱えながらも、どこかで生きていてほしいという願いを持ち続けておられたのではないかと思います。そして、遺骨が発見された日をご命日と定められました。その選択には、「どこかで生きていると信じたかった」というお気持ちが託されていたのではないかと感じます。
『大涅槃経』生者必滅しょうじゃひつめつ会者定離えしゃじょうり理ことわりであり、誰も避けることはできません。しかし、肉体は滅びても、亡き方々とのご縁は決して消え去るものではなく、私たちの心の中に生き続けます。
また、「天災は忘れた頃にやってくる」や、「災難のときには災難に遭うがよろしい」(良寛)という言葉があります。被災された方々にとっては何の慰めにもならず、むしろ憤りを感じることもあるかもしれません。悲しみや苦しみと向き合い、それを受け入れることは、ご本人にしかできません。
しかし、私たち支援する者がどのように寄り添い、手を差し伸べるかが何より大切なのだと思います。その支援の形は一つではなく、多様な手立てが求められますが、真に心が救われることは決して簡単ではありません。
記憶は時とともに薄れていくものですが、それでも決して忘れてはならないことがあります。
「忘己利他もうこりた」――自らのことを忘れ、他者のために尽くすという教えのもと、悲しみを共にし、支え合うことが、今を生きる私たちに求められているのではないでしょうか。
あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。ご家族皆様方のご健康とご多幸、そしてさらなるご活躍を心よりお祈りいたします。
仏教においても、蛇は「守護」や「智慧」の象徴である一方で、「煩悩」や「執着」といった克服すべき課題の象徴でもあります。蛇の脱皮や再生という特性は、仏教の輪廻や悟りの道に通じる要素を持ち、深い精神的な意味を秘めています。巳年はこれらの教えに立ち返り、自らの内面を見つめ直す良い機会と捉えることができます。
また、ことわざに関連させて言えば、「蛇足だそく」という言葉は、中国の故事に由来します。蛇を描く競争で、完成した絵に足を描き加えたため、蛇ではなくなり失敗したという話が元になっています。このエピソードは、本来不要なものを加えることで本質を損ない、失敗を招くことを戒めた教訓です。 「蛇足」には、「余計なものを付け加えることで、かえって物事を損ねる」という意味があり、物事の本質を見極め、無駄を省くことの重要性を教えてくれます。。 ※仙台市八木山動物園(八木山動物公園フジサキの杜)の爬虫類館がなくなるというので、あわてて出かけ、堂々とした青大将を描き、長泉寺の応接室に画家の及川聰子先生がヘビの絵を掛けて下さいました。毎日見ていると、白ヘビもやさしいものです。
AI(ChatGPT)に「巳年」「蛇足」について聞いてみました。
巳年と仏教の関連巳年は十二支の「巳(蛇)」に該当し、蛇は仏教とも深い関わりを持つ象徴的な存在です。以下にその関連性を説明します。
- 蛇と仏教の象徴
仏教では、蛇(または竜蛇)は古代インドや東アジアの伝統において重要な象徴とされています。仏教の中で蛇は両義的な意味を持つことがあります。
守護と智慧の象徴
蛇や竜蛇は、守護神や智慧の象徴とされることが多いです。たとえば、仏教の守護神である「ナーガ(龍神)」は、蛇や竜として表現されます。ナーガは仏陀が説法した際に雨を防いだり、仏陀の教えを守ったりする役割を担っています。このイメージは、蛇や竜が地球や水のエネルギーと結びつけられることに由来します。
煩悩の象徴
一方で、蛇は煩悩や執着の象徴ともされています。仏教では、三毒(貪・瞋・痴)のうち「瞋(しん)」(怒りや憎しみ)は蛇に例えられます。蛇が威嚇し、攻撃的になる姿が怒りに通じるためです。このように、蛇は克服すべき感情や煩悩を象徴する存在でもあります。
- 十二天との関連
仏教の十二天の中では、「毘沙門天」が巳年に関連付けられることがあります。毘沙門天は財宝や武運を守護する神であり、仏教徒にとって重要な存在です。巳年にあたる人は、毘沙門天の加護を受けやすいとも言われています。
- 蛇と輪廻の象徴
蛇は脱皮を繰り返すことから「再生」や「変化」を象徴する動物とも見なされます。この特徴は、仏教の教えである輪廻転生(生死を繰り返し新しい命を得ること)や悟りへの道を象徴していると解釈されることがあります。
- 仏教行事や祈願
巳年は蛇に関連した信仰や行事が行われることもあります。特に蛇を祀る神社仏閣では、巳年にちなんだ祈願が行われ、財運や健康を祈ることが一般的です。例えば、蛇を神聖視する寺院や仏像には、蛇が絡みついた像などが見られます。
まとめ
巳年に関連する蛇は、仏教において「守護」や「智慧」の象徴である一方、「煩悩」や「執着」といった克服すべき課題の象徴ともされています。蛇の脱皮や再生という特性は、仏教の輪廻や悟りの道に通じる要素を持ち、深い精神的な意味を秘めています。巳年はこれらの教えに立ち返り、自らの内面を見つめ直す良い機会と捉えることができます。
「蛇足」について
- 蛇足の由来
「蛇足」は中国の故事に由来し、蛇を描く競争で、完成した絵に足を描き加えたために、蛇ではなくなり失敗したという話が元になっています。このエピソードから、本来不要なものを加えることで本質を損なうことを戒めた言葉です。
- 仏教の教えとの関連
仏教では「中道」という教えがあり、これは「極端を避けてバランスを保つこと」を重視します。「蛇足」を仏教的に解釈すると、次のように関連付けられます。
執着の克服
仏教では、無駄な欲や執着を「煩悩」として戒めます。「蛇足」に該当するような余計な行為や欲望は、執着の一種と見なされるため、仏教の理想である無執着(むしゅうじゃく)や無為自然(むいしぜん)を損なう行為と考えられます。
智慧をもって本質を見極める
仏教の教えでは、物事の本質を見極める「智慧」が重要とされています。「蛇足」のように、本質を理解せず余計なことを加えるのは、智慧が欠けている状態といえます。このため、仏教的には「本来の目的や意義を正しく理解し、余計なことをせずに簡素に進めるべき」と教えられています。
- 蛇と煩悩の象徴
仏教において、蛇は煩悩を象徴する動物の一つです。特に「瞋(しん)」(怒りや憎しみ)は蛇の威嚇や攻撃性に例えられます。「蛇足」の話も、執着や過剰な行動による失敗を戒めたものであり、仏教的には煩悩の制御や智慧の実践を示唆しているといえるでしょう。
- 無駄を省く生き方
仏教では「簡素」「無駄を省く」ことを理想的な生き方の一つとしています。「蛇足」を避けることは、仏教の修行における中道や質素の実践とも一致します。たとえば禅の教えでは、日常生活や思考において不要なものをそぎ落とすことが重要視されており、「蛇足」のような行為は避けるべきものとされます。
前回は少子高齢化・多死社会、そして人口減少に関して少し私見を述べさせていただきました。 まもなく今年も「お盆」の季節を迎えます(当地方は旧盆で8月ですが)。 一昔前は夏休み真っ最中の旧盆の帰省は民族大移動などと形容されたこともありますが、最近はお盆の帰省もそしてお正月のそれも様変わりしているようです。
さて、最近はこれまた少子化の顕著な影響だと思うのですが、都会に出たまま郷里に戻ることなくそのまま定住される方が増え、いわゆる「墓じまい」をされる方が増えてきました。全国的な統計では10年前と比べると倍増の約15万件強になっているとのことです。コロナ禍以降は「小さなお葬式」に象徴されるように「家族葬」も増加の傾向にあり、また年回忌のご法要も簡素化される方が増えてきたと実感しております。 これもご兄弟やご親族の減少が少なからず影響しているのではないかと思われます。
「墓じまい」に話を戻しますと、一部の報道によれば、「墓じまい」の際に法外な金銭を要求する心ないご寺院様もあるとかで唖然とするばかりですが、それはともかく時代の流れで「墓じまい」せざるを得ないご事情があることもよく理解されるところです。
しかし、たとえ「墓じまい」したとしても、ご先祖様が長らくここ「角田」、菩提寺「長泉寺」にあったという事実は消えるものではなく、郷里を離れた方々がたまには帰ってみたいと思う「角田」、お詣りしてみたいと思う菩提寺「長泉寺」であり続けたいと思う昨今です。内外の清掃に心を配り、みなさまそしてご先祖の御霊が気持ちよく帰れるよう努力してまいります。
失礼いたしました。
いま我が国は、少子高齢化・多死時代の真っ只中にあります。少子高齢化・多死時代は、人口問題に直結しています。角田市を例にとってみますと、1958年(昭和33年)の市政施行時に約3万6千人であった角田市の人口は、いまでは2万7千人を割り込む状況となっています。(令和6年4月30日現在、人口総数26,707人)実に市政施行時から約4分の1の人口が減少したことになります。
他方、多死時代に眼を転じてみると、私が学生時代から関心を寄せていた音楽家や俳優の訃報に接することが最近多くなり、とても寂しく、また残念に思っています。亡くなった方々は、皆なそれぞれにそれなりの年齢に達しているので、仕方のないことと言えば仕方のないことなのですが、やはり悲しく思うとともに無常なる時の流れを感ぜずにはおられません。
いつまでも若いと思っていた私も今春、古稀を迎え感慨深いものがあります。
今までは 人のことだと 思うたに おれが死ぬとは こいつたまらん。
このようなシャレた心境にはまだ至っておりませんが、 「諸行無常」を念頭に、自分の身辺をたえず見つめ直してみたいと思っている昨今です。
毎日はつらつと登園して来る幼稚園の園児を見ていると、自然と元気が湧いてきます。「諸行無常」であるからこそ、はつらつと今日も楽しくも頑張っていきましょうと園児さんからは教えてもらっているかのようです。願わくは角田市に子育て世帯がどんどんと増えて、活気ある角田市になりますようにと願わずにはおられません。